相続人関係図・相続財産目録
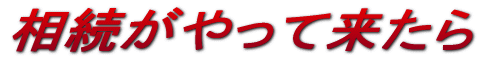
相続人関係図・相続財産目録 |
|
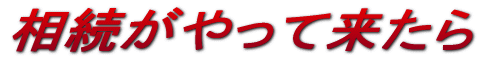 |
相続人関係図・相続財産目録って |
相続人関係図・相続財産目録って
相続人関係図・相続財産目録とは、 |
|
|
| ★相続がやって来たら ★相続手続 ★遺言・生前贈与 ★自筆証書遺言 ★公正証書遺言・秘密証書遺言とは ★遺言書がある場合 ★遺言トラブル ★遺留分とは ★法定相続って ★法定相続分って ★相続人欠格・相続人廃除って ★遺産分割協議とは ★相続人関係図・相続財産目録とは ★寄与分と特別受益って ★相続放棄と限定承認って ★名義変更するには ★プロフィール ★財産評価 ★土地以外の財産評価 ★その他の財産評価 ★相続税 ★相続税税額控除 ★贈与税 |
相続人関係図と相続財産目録について 相続人関係図とは 遺産分割協議をする前に、法定相続人を確定しておかなければなりません。 法定相続人を確定しておかなければ、遺産分割協議を行い、遺産を分割した後で、新たな相続人がでてきたら、遺産分割協議はまたやり直しになってしまいます。 そこで相続人を調べ、相続人関係図を作っておくのです。 ●どうやって調べるのか? 本籍地の市町村役場へ行き、戸籍謄本の交付を申請します。ここで豆知識ですが、戸籍の謄本と抄本とは、何が違うのでしょう? 答え 謄本・・・戸籍の全部 抄本・・・その戸籍に表示されている人の一部のみ 話を戻して、戸籍の謄本を請求します。そして、この戸籍には、以前にどこの戸籍から入籍があったかを調べていくわけです。 要するにその戸籍から、この戸籍より前の戸籍を調べていくわけです。 除籍謄本もしくは改製原戸籍(昭和32年法務省令27号によって新たに編成されたものである場合)を交付申請していくこととなります。 ●転籍の場合 この本籍に転籍する前の本籍地を管轄する市区町村に対して除籍謄本を請求する。 ●養子縁組の場合 この戸籍に入籍する前の戸籍謄本を請求することになります。 ●認知の場合 認知した子どもが同籍している母の除籍謄本を請求することになります。 このようにして戸籍をたどっていき、法定相続人を確定していきます。先祖代々の家計図などを想像してもらうとわかりやすいと思うのですが、そんな感じに相続人関係図を作っていくのです。 相続財産目録とは まず、民法でいう相続財産の定義ですが「相続人は相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。」となっています。 ■相続開始のときとは 被相続人が亡くなられた日ですね。 ■権利義務とは 権利とは、不動産・借地権・借家権・株式・ゴルフ会員権・預貯金・貴金属・現金等のプラスの財産のことですね。 義務とは、借入金・通常の連帯保証債務等のマイナスの財産のことですね。 ■被相続人の一身に専属したものとは ・身元保証の義務など 生活保護法にもとづく保護受給権は被保護者自身の最低限度の生活を維持する為にその個人に与えられたものであるため、相続財産とはならないわけですね。 ・生命保険金・退職金 法律や就業規則などによって、受給権者の範囲と順序が決まっており、その定められた者の固有の権利とみなされているから、相続財産とはならないわけです。 *相続税法上は、「みなし相続財産」として相続税が課税されます。 また、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべきものがこれを承継する」とされています。 すなわち、位牌、遺骨などは相続財産には、入らないということなんですね。 このように相続財産を確定していき、相続財産目録を作っていくことになります。 この相続財産目録をつくることは、遺産分割協議をするうえで、また相続税を支払う場合には必須のことなのです。 明らかに相続税がかからない場合には、おおまかなものでも良いですが、かかるかかからないかわからないときは、やはりつくるべきでしょう。 |
| Copyright(C)相続がやって来たらAll Rights Reserved |
| 当サイトはリンクフリーです 相互リンクも募集しています メールでお気軽にご連絡ください |
| 免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします |