遺産分割協議
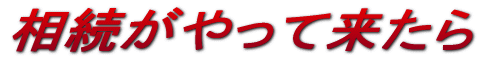
遺産分割協議 |
|
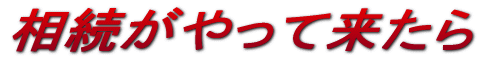 |
遺産分割協議とは |
遺産分割協議とは
遺産分割協議についての基礎知識を |
|
|
| ★相続がやって来たら ★相続手続 ★遺言・生前贈与 ★自筆証書遺言 ★公正証書遺言・秘密証書遺言とは ★遺言書がある場合 ★遺言トラブル ★遺留分とは ★法定相続って ★法定相続分って ★相続人欠格・相続人廃除って ★遺産分割協議とは ★相続人関係図・相続財産目録とは ★寄与分と特別受益って ★相続放棄と限定承認って ★名義変更するには ★プロフィール ★財産評価 ★土地以外の財産評価 ★その他の財産評価 ★相続税 ★相続税税額控除 ★贈与税 |
遺産分割協議とは 遺言が無い場合には、相続人間の話し合いによって遺産を分割することになります。 遺産の分割に時間制限はありません。 遺産分割協議は全員一致で決めなければ、成立しないんです。 もちろん、多数決で決めることもできません。 法定相続人の一人でも意思の合致がなければ、成立しないものなのです。 また、相続人たる地位に疑問のある者(婚姻外の子など)を無視して分割協議をしても、後日その者が相続人であることが確定すると無効になるんです。 逆にいえば、相続人の全員の合致があれば、どのような遺産分割をしてもいいわけなんです。 そして、遺産分割協議書を作っていくわけです。 ●未成年者がいる場合には 未成年者には法律行為能力がないので、法定代理人(普通は親ですね)が代わって法律行為をします。 代理人には原則親権者がなります。 しかし、相続の場合、親権者も相続人であることがあります。 そんなときには、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。 ●被後見人がいる場合 被後見人が相続人である場合には、後見人が代わって相続手続をします。 遺産分割協議書の作り方 遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、全員の署名・押印をして各自1通づつ保管することになります。 では、遺産分割協議書は絶対に作らなければならないのか?絶対ではないんですね。 ただ、作らないといけない時があるんです。 相続による不動産などの所有権の移転登記をする時には、添付書類として必要になります。 まあ、後々争いにならないように、証拠書類として作っておいた方がよいと思いま す。 ■胎児がいる場合 胎児は生まれたものとみなされ、他の相続人同様の相続権があります。問題は、胎児は遺産分割協議に参加できないということなんです。 もしかしたら死産の可能性もあるわけです。 生まれるのを待って代理人を立てて遺産分割をすることになるでしょう。 そのときには、特別代理人を選任することになります。 母親も相続人ですから、代理人にはなれませんので。 *利益相反行為とは、上記のような場合のことをいいます。 親権を持っていいる父・母とその子の利益が相反する行為については、親権を行うものは、その子のために特別代理人を選任しなければならないこととなっているのです。 この場合家庭裁判所に特別代理人の選任の請求をし、特別代理人が選任されてから遺産分割をすることになります。 ただ、特別代理人を選任する手続はかなり大変なようです。 一般的には、法定相続分で共有のまま相続することもあるようです。 ■相続人が行方不明になっている場合 相続人が行方不明になっている場合には、行方不明の人を除いて、他の者だけで協議することはできないんです。 利害関係人または検察官が家庭裁判所に請求して、行方不明になっている人の代理人である「財産管理人」の選任をしてもらうことになります。 行方不明者の生死が、7年間わからないときは、「失踪の宣告」をし、死亡したものとして、他の相続人だけで遺産分割協議をすることになります。 ●遺産分割協議書作成の注意点 ・遺産争いの余地を残さないよう作成する ・被相続人を明らかにする ・相続人を確定する ・不動産については、登記簿謄本に記載されているとおり記載する ・預貯金は預貯金名義人、口座番号によって特定する ・相続人が署名・押印する(印鑑証明書の印鑑) ・遺産分割協議書が2枚以上になるときは、用紙から用紙のところへ契印する ・訂正する場合には捨印を押す ・印紙は必要ありません *作成後に新たに相続財産が見つかった場合のために、その財産について分割協議をするとともに、先になした遺産分割協議書は以前として有効である旨の確認をする。 |
| Copyright(C)相続がやって来たらAll Rights Reserved |
| 当サイトはリンクフリーです 相互リンクも募集しています メールでお気軽にご連絡ください |
| 免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします |